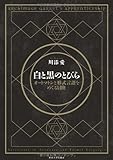モールス符号の「地図」
謎の遺跡
ある遺跡を考えます。唯一の入口からその遺跡の中に入ると2つの扉があり、扉にはそれぞれ「・」「ー」という2種類の文字が書いてあります。

試しに「・」と書かれた扉を開き、隣の部屋に移動すると、またもや「・」「ー」と書かれた2つの扉があります。先ほどの部屋と違うのは、扉と扉の間に「E」と書かれていることです。

今度は「ー」と書かれた扉を開き、隣の部屋に移動すると、やっぱり「・」「ー」と書かれた2つの扉があって、その間には「A」という文字が書かれていました。
……この遺跡を探検すると、どのような間取りになっているのでしょうか?
遺跡の「地図」
ある人がこの遺跡を調査した結果、以下の地図のように部屋がつながっていることが判明しました。一番上が入口の中の部屋で、下に行くほど遺跡の奥に対応します。

この地図を使えば、好きな部屋に迷わず行くことが可能になります。
たとえば、「A」と書かれた部屋に行きたければ、最初に「・」の扉を開き、次に「ー」の扉を開けばよいことになります。この経路を地図上に描くと、以下のようになります。

他にも、「B」と書かれた部屋に行きたければ、最初に「ー」の扉を開き、それから「・」→「・」→「・」と扉を開いていけばよいことになりますね(下図)。

それ以外のどのアルファベットの場合にも、適切な道筋を辿ることによってそのアルファベットが書かれた部屋に行くことが可能です。
地図上の道筋リストとモールス符号
ここで、「Aと書かれた部屋に行く道筋」「Bと書かれた部屋に行く道筋」……「Zと書かれた部屋に行く道筋」をリストアップしてみます。前章の例では、「・」→「ー」と扉を開けばAの部屋に辿り着くので
A: ・ー
となり、「ー」→「・」→「・」→「・」と扉を開けばBの部屋に辿り着くので
B: ー・・・
のようになります。同様に全てのアルファベットについてリストアップすると、以下の表のようになります。先ほどの「地図」と比べてみて下さい。
| 文字 | 道筋 | 文字 | 道筋 |
|---|---|---|---|
| A | ・- | N | -・ |
| B | -・・・ | O | --- |
| C | -・-・ | P | ・--・ |
| D | -・・ | Q | --・- |
| E | ・ | R | ・-・ |
| F | ・・-・ | S | ・・・ |
| G | --・ | T | - |
| H | ・・・・ | U | ・・- |
| I | ・・ | V | ・・・- |
| J | ・--- | W | ・-- |
| K | -・- | X | -・・- |
| L | ・-・・ | Y | -・-- |
| M | -- | Z | --・・ |
勘のいい方は気が付いたかもしれませんが、これはモールス符号の対応表に他なりません。…というか、タイトルに思いっきり「モールス符号」と書いちゃっているので、何を勿体ぶってるんだという感じですね。
「地図」を用いたモールス信号の解読
前章で述べた「道筋リスト」がモールス符号の対応表であるという事実から、冒頭の遺跡の正体はモールス信号の解読装置であったと言うことができます。なぜなら、例えば「-・-・」というモールス信号が与えられたとすれば、「-・-・」の順に扉を開いて行った先に解読後のアルファベット「C」を見つけることができるからです。
遺跡が「・」と「ー」によるモールス信号の解読装置であることが分かったところで、先ほどの「地図」を見直してみましょう。

この地図は、一般的なモールス符号表よりもモールス信号の解読に適しています。なぜなら、地図の一番上からスタートし、「・」や「ー」といった信号を受け取るたびに枝分かれ先へ進んでいけば、行き着いた先のアルファベットを見るだけで解読できるからです。同じ解読作業を以下の表(再掲)で行おうとすると、暗記でもしていない限り大変だと思います。
| 文字 | 道筋 | 文字 | 道筋 |
|---|---|---|---|
| A | ・- | N | -・ |
| B | -・・・ | O | --- |
| C | -・-・ | P | ・--・ |
| D | -・・ | Q | --・- |
| E | ・ | R | ・-・ |
| F | ・・-・ | S | ・・・ |
| G | --・ | T | - |
| H | ・・・・ | U | ・・- |
| I | ・・ | V | ・・・- |
| J | ・--- | W | ・-- |
| K | -・- | X | -・・- |
| L | ・-・・ | Y | -・-- |
| M | -- | Z | --・・ |
逆に、「アルファベット→モールス信号」の変換を行うには、アルファベット順に並んでいる表の方が良いでしょう。一長一短ですね。
なぜこのように符号化されているのか?
再び「地図」を見てみます。

これを見ると、なぜA〜Zがこんなにバラバラに配置されているのだろう?という疑問が生じます。上からABCと並べればよさそうなのに、2段目にEとT、3段目にはI、A、N、Mといった配置になっています。
その答えは、Wikipediaの以下の記述にあります。
策定については、標準的な英文におけるアルファベットの出現頻度に応じて符号化されており、よく出現する文字ほど短い符号で表示される。例を挙げると、Eは(・)、Tは(-)とそれぞれ1符号と最短である。逆に使用頻度が少ないと思われるQは(--・-)、Jは(・---)と長い符号が制定されている。
なるほど、使用頻度の高い文字が短い符号で表せるようになっていたわけですね。納得納得。
ドローンが作れないので輪ゴムでヘリコプターを作る
はじめに
デイリーポータルZの記事で、最近はやりのドローンを自作しようと試みていました。なんだか楽しそうです。portal.nifty.com
これに触発されてドローンをつくりたいなと思ったのですが、お金もかかるし飛ばせる気もしないので、少々(かなり)妥協することにしました。輪ゴムヘリコプターです。
輪ゴムヘリコプターとは、文字通り輪ゴムの力で飛ぶ小さなヘリコプターです。
小さいころに下のような飛行機を作った*1ことがあったのですが、それと同じ方法でプロペラを回します。

袋入りライトプレーン A級ペガサス (中級者向) LP-04
- 出版社/メーカー: スタジオミド
- メディア: おもちゃ&ホビー
- この商品を含むブログを見る
*1:竹ひごをロウソクで炙って曲げたり、雁皮紙を翼にはったりするやつ。懐かしいなあ。
ハコベのうぶ毛に潜む規則性
はじめに
春が来ました。様々な植物が花を咲かせており、その生命力に驚かされます。ということで、雑草の本を読んでから花見ついでに野に出てみることにしました。
以下の本ではカラー写真付きで様々な雑草の豆知識が得られるので、これを読んでから地面を眺めると、今まで無視していた雑草たちが個性を主張してくるような気分になり親近感がわきます。良く見てみると沢山の雑草が生えているのですが、大人になるにつれて気にも留めなくなってしまうものですね。

- 作者: 田中修
- 出版社/メーカー: 中央公論新社
- 発売日: 2007/03
- メディア: 新書
- 購入: 1人 クリック: 15回
- この商品を含むブログ (10件) を見る
以下では、「ハコベ」という雑草に注目し、その茎に生えるうぶ毛の方向の規則性について述べていきます。この規則性は本で読んだのではなく少しだけの観察から見出したものなので、あまり鵜呑みにはしないでくださいね。
ざまあ見ろ、旅に出てやったぜ
突然ですが、都会に飽きたので一人旅に出ました。
時間だけはある暇人なので、国内旅行をする際は基本的に青春18きっぷを使うことにしています。おしりが圧迫されますが、移り変わる景色を眺めながら読書をするのもなかなか良いものなのです。
で、今回も鈍行で東京を脱出したのですが、東京から出る度になんだか「ざまあ見ろ」という気持ちになるのです。別に誰かに恨みがあるわけでもないし、どこがどう「ざまあ見ろ」なのか全くわからないけれど、とにかくせいせいするわけです。この傾向は、どうやら電車の一人旅のときに強くあらわれるように思われます。
そんなことを旅ごとに感じていたのですが、村上春樹の『辺境・近境』という旅行記にも似たような気持ちが書かれていることを最近になって知りました。無人島に来た村上春樹は、以下のような気分になります。
続きを読む座標軸に基づく芸術の分類と、音楽的・絵画的文章の話
はじめに
先日の記事は「音楽とは時間軸上のぽんぽこであり、…」などという妄言から始めました。「ぽんぽこ」はその場で心に浮かんできただけですが、ぽんぽこであろうとなかろうと、音楽が時間軸上の芸術であることは確かだと思います。1つの絵画は3秒でもそれなりに分かりますが、1曲を3秒で楽しむことは難しいですよね。
ここでは、時間や空間といった概念に基づいて理系的な視点で芸術を分類してみます。芸術系どころか文系でもないので適当なことを言っているかもしれませんが、いつものことなので。